症状の役割
自閉症について最初の報告をしたカナーという児童精神科医は、子どもの身体症状に以下の5つの意味があると捉えています
- 入場券としての症状
- 危険サインとしての症状
- 安全弁としての症状
- 問題解決の手段としての症状
- 厄介者としての症状
カナーは子どもの身体症状として捉えていますが、いくつか大人にも通ずるところがあるので紹介します。
そもそも、一般的には症状に役割があると考える人は少ないのかもしれません。しかし、我々心理士にとってそのような考えはまず最初に頭に浮かぶものです。すなわち、
〈このクライアントのこの症状は一体どのような役割、意味を持っているのだろうか?〉
「入場券としての症状」と「安全弁としての症状」
入場券とはつまり、きっかけのことです。
医者やカウンセラーの元にやってくる相談者、患者は何らかの症状を訴えます。精神的なものや肉体的・生理的な症状など様々な症状があり得ます。
このように「症状を取って欲しい」として来られた相談者に対して、ただ症状を取ろうとするのではなく、症状をある種の入場券(つまりきっかけ)としてやって来られた相談者の背後にはどんな課題や問題が潜んでいるのだろうか?という捉え方が、この入場券という表現には含まれています。

我々カウンセラーとしては、この観点は大切にしたいものです。
というのも、症状には「安全弁としての機能」も備わっていて、症状を単純に除外してしまうことが良いことだけではないからです。
よく例として挙げられるのが、風邪をひいたときの「熱」です。風邪をひいて、症状としての熱が出ると、頭がぼんやりとして苦しい。早く熱を下げたいと思う。しかし、この熱という症状には、体内のウイルスが増殖しないようにするための、身体の自然な反応でもあるわけです。
(例:熱を上げることによって免疫細胞を活性化させる)
ずっと熱が出続けるわけにもいきませんが、かといって、熱が出たらすぐにそれを取り去ってしまおうとすることも問題です。身体の自然の理に反しているというわけです。

精神的な症状にも、この捉え方は当てはまることがあると思います。
学校や会社に行こうとすると、身体が重い、だるい、熱が出る、吐き気がする・・・
人目が気になって外出が出来ない、自分で自分を醜いと思う、人が怖い、やる気が出ない、動くためのエネルギーが湧かない・・・
症状が取り除かれてしまったら、結構困ることもあるのです。
だって、そうではないでしょうか。熱もなくて身体も軽かったら、学校や会社に行くことが出来てしまいますから。だから、実際に本当にリアルに身体が重くなるし吐き気もするし熱も出るのです。
そしてこのことを意識的にも無意識的にも、クライアントは知っていることがあります。
では、症状を取り除かれると困るクライアントは、一体何のために精神科医やカウンセラーの元を訪れるのでしょうか?
症状そのものが問題なのではなく、症状が出るに至った経緯や背景にこそ問題があると感じているのではないでしょうか。
少なくとも心理カウンセラーにとっての現実は、
「クライアントが何を考えていようと、それらの症状を伴って、ここへ来た」ということです。
最も大事なのは、症状をきっかけにしてきたその人を大切にして話を聞かせて頂くことなのです。
最悪な状態を回避するために、症状としての体調不良や精神的不調に悩まなければいけないことになった。
そこまでして自分を守らなければならなかったのはなぜなのか?そこに耳を澄ませる必要があります。
危険サインとしての症状

また、症状には危険サインとしての意味もあることを忘れないようにしたいものです。
身体のどこかが痛かったり、目に見えない内部の組織に異常があったりすると、様々な形で表面化してきます。
心も体も同様に。
無視し続けると、サインはもっと大きくなって、誰にでも読み取れるくらいひどい症状として出てきてしまうかもしれません。
自分の身体の声、心の声に、耳を傾ける習慣を身につけたいものです。
私も数年前、肉体労働をしていたことがありました。
とある仕事では、大きな環境の変化から、仕事中に突然吐き気を催したり、
また別の仕事では、身体のあちこちからじんましんのような湿疹が現れたりもしました。
私の場合、そういった症状に共通したのは、それらの仕事に対してどこか「乗り気でない気持ち」があったり、またどこか「無理をしている」ところがあったりしました。
とてもとても嫌な仕事なのに、言われるがまま、残業をする。時には土日も出勤して、何のための仕事なのかさっぱり分からないような心境でした。
そうした時に現れたあのじんましんは、かゆくてたまらない厄介な代物でしたが、自分の心の声に耳を傾けるきっかけにはなったと思っています。
問題解決の手段としての症状
一言で症状と言っても、様々なものがあります。
問題解決の手段としての症状を考えるときには、一言で「体調が悪い」といっても、さらに具体的に掘り下げていきます。
体調が悪い。具体的には?頭が痛い。吐き気もする。
そこで「なぜ頭が痛いという症状なのか?」「なぜ吐き気がするという症状なのか?」という観点を持つ事が重要です。
頭が痛いということは、単に物理的に頭が痛いということなのか?
それとも、頭が痛くなるほどたくさんの考え事にさいなまれているということなのか?
吐き気がするということは、単に物理的に胃の調子が悪くて吐き気がするということなのか?
それとも、何か吐き出したい気持ちや思いがたくさんあって、それが吐き気として感じられるのか?
実は、体調不良などで訴えているその症状の一つ一つが、実際の問題解決の遠回しなヒントになっているかもしれません。
症状は、問題を何とか解決しようと必死に考え出されたメッセージであり、具体的な行動としての意味合いも持っていると思われます。
体調不良と同様に、精神的な不調・精神的な症状にも様々な意味が隠されているでしょう。
- 抑うつ気分
- 不安
- 恐怖
何が不安なのか?何が怖いのか?
学校が?先生が?親が?上司が?なんとなく漠然と?将来が?過去が?・・・
問題を解決するために、症状はヒントになり得ます。
症状を誰かに訴え、聞いてもらい、一緒に考えることこそが、症状の持つ問題解決の手段としての役割であると考えます。
厄介者としての症状
症状には、何か異常が起こっていることを知らせるサインとしての意味があることは既に述べました。
そのサインは、自分自身に対してだけでなく、周囲の人にも知らせるためのものです。
症状のつらさ、巻き込まれている出来事のつらさ、それらによって生じる怒りや悲しみ・・・
そういったものを周りの人に伝えることによって、注意や興味関心をひく意味が症状にはあります。
また、家族や学校、社会など集団の中において、
何か大きな問題が起こっているのに、誰もその問題に着手しなかったり、対処しなかったり、見て見ぬフリをしていたりすると、
仕方なくその人が代表して症状を発症して、病気にならなければならないこともあります。
それが厄介者としての症状と言えるでしょう。
参考・引用文献
・Leo Kanner(著)、黒丸正四郎(翻訳)、牧田清志(翻訳) 『カナー児童精神医学』第2版 医学書院 1974年
カウンセリングの案内
*カウンセリングオフィスともしびは事前予約制です。
・ご予約はこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)から。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)

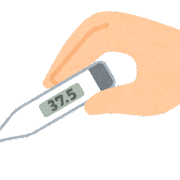


コメント