マインドフルネスとは?
マインドフルネスとは、あるがままの自分の状態に気づく事です。
マインドフルネスの先駆けであるジョン・カバットジン博士はマインドフルネスを
「意志を持ってこの瞬間に注意を払い、自分で評価を下さない」
ジョン・カバットジン(著)、貝谷久宜(監訳)、鈴木孝信(訳) 『マインドフルネスのはじめ方 今この瞬間とあなたの人生を取り戻すために』
と定義しています。
マインドフルネスという言葉自体は比較的新しく、近年になって心理療法の一つとしても用いられるようになってきましたが、マインドフルネスと似た考えを提唱していた先駆者は他にもいました。
例えば、日本の心理療法で言うと森田療法が近いと思われます。
森田療法では、神経症的なとらわれ(一つの物事に執着し、取り去ろうとする考え)を無理に取り去ろうとするのではなく、あるがままの自分として受け入れていくことを推奨しています。
取り去ろう取り去ろう、楽になろう楽になろうという意識が、より深い底なし沼の考えに人を誘っていきます。でればいっそ、苦しみを苦しみ抜いて、悲しみを悲しみ抜くようなある種の開き直りのような態度を取ってみるのも一つの手であるのかもしれません。
マインドフルネスは、「意識して考えるモード」から「自然に気づくモード」へと切り替える事だとも言えます。
私たちは、日常的に「考えること」がデフォルト設定になってしまっています。
マインドフルネスでは、考えることを一時的に放棄し、考えることから解き放たれ、
気づきの海に身を投げ出すようなものです。
お風呂に入っている時や就寝前のリラックスした状態でいる時、ふと色んなアイディアが思い浮かぶことは誰もが一度は経験したことがあるでしょう。
このようなリラックス状態、価値判断もせず、常に起こっていることに気がつくような「態度」「あり方」のことをマインドフルネスというのです。
なぜマインドフルネスをすすめるのか?
人は、いつも何かを目指している
人は思考する動物です。
思考は物質です。
思考は、今までの人類の歴史を振り返ってみて分かるように、様々な物を作り上げてきました。
様々な発明、建物、道具、、、戦争、宇宙ロケット、インターネット・・・等々
挙げればキリがありません。
思考は正しく作用すれば、人の生活をより便利で生きやすくするためのツールになりますが、
反対に、人を悩みの渦の中に閉じ込めてしまうこともあります。
日々の思考は癖になり、パターン化します。
そうすると、人はその思考を自分自身であると錯覚し始めます。
思考はまた、いつも何かを目指しています。
達成すること、認められること、受け入れられること、努力すること、今よりもっと優れること・・・等々
マインドフルネスは、何もしないをすることです。
目指すこととは逆のことをするのがマインドフルです。
いや、するというよりむしろ、「在る」「ある」。ただあるだけの状態。自分が自分として在るだけの状態。そこに努力など必要ありません。目標も必要ありません。
私は、努力などしなくても既に私であるからです。
この無行為。努力無しの全身全霊で自分であること、これがマインドフルネスです。
マインドフルネスをすすめるのはなぜか?
・すべきことなど何も無いこと
・一切の努力のない状態が誰にでもあるということ
を知ってもらいたいからです。
思考から自由になり、思考に振り回されないようにするために、マインドフルネスを活用すると良いと思います。
マインドフルネスを実行する
考えるな、感じろ Don't think!feel.
マインドフルネスを実践するとは、どういうことでしょうか?
実は、これはそんなに簡単な事ではないと私自身は考えています。
なぜなら、マインドフルネスの定義にもあるように、マインドフルネスには、
「自分で評価を下さない」
という非行為が含まれているからです。
言葉上「~しない」は行動ではありません。つまり、
マインドフルネスをするとは「~しないをする」という一見矛盾したことを言っている事になってしまうのです。
では、マインドフルネスは一体どのように実践すれば良いのでしょう?
つまり、この瞬間に起きているあるがままの自分の状態に注意を向け、その上で価値判断をしないということを、
一体どのようにすれば良いのでしょうか?
一つ推奨される方法としては、呼吸に注目する方法です。
呼吸は今この瞬間にも起きています。生きている限り起きていない事がないので、観察の対象としてはもってこいです。
まずは呼吸を感じてください。
考えるのではなく、感じるのです。(ブルース・リーも似たようなことを言っていました)
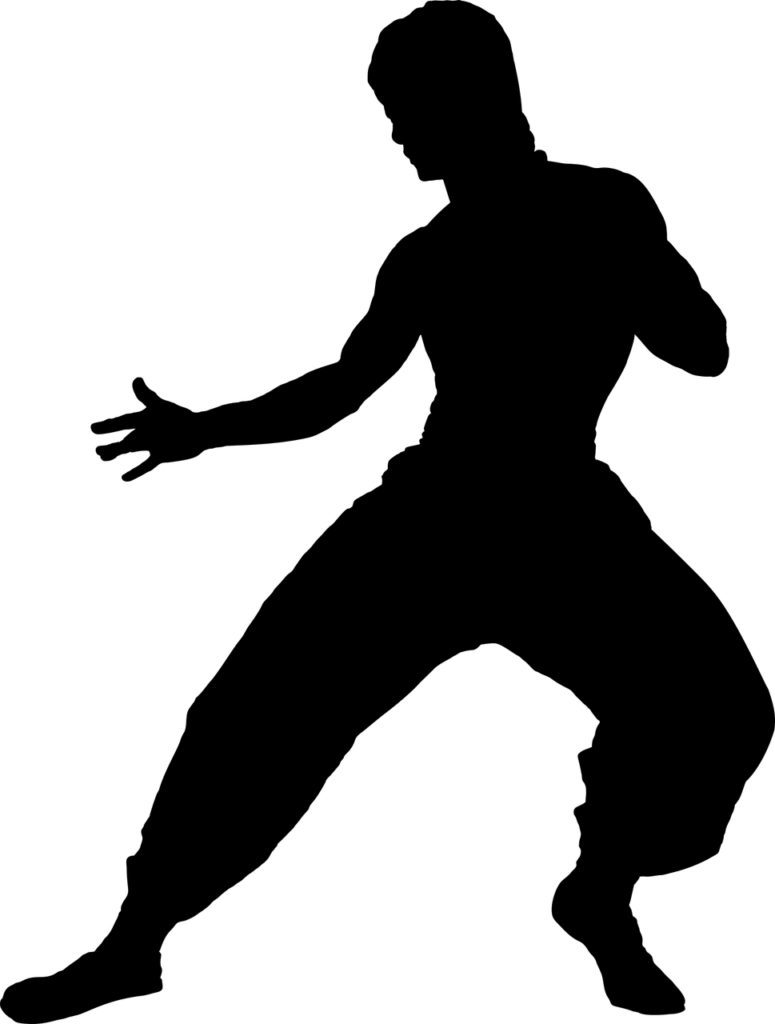
マインドフルネスは、いつ、どのような場面であっても出来ることです。
見る、聞く、味わう、触れる、嗅ぐ、、、5感を通じたあらゆる感覚と、即座の理解に耳を澄ませること。
これらは単純であるがゆえに、とても難しい。
今この文章を読んでいる皆さんは、一日たった5分でも、TVも携帯も消して、
一つの事に注意を向けてみたことがあるでしょうか?
やってみたことがない人は、今からこの画面を閉じて、今起こっていることに注意を向けてみてください。注意を向ける対象は何でも良いです。
試しに呼吸にでも。
やってみると分かる事があります。5分間注意を向けることは簡単ではないと言うことです。
すぐに退屈になって他の事をしたくなるかもしれません。新しい用事を思いつくかもしれません。
あるいは、様々な思考が邪魔をしてくるかもしれません。「こんなことをやって何になる?」と
思考は、いかに空白の時間を嫌うのかが良く分かります。
でも、思考がもたげることをダメなことと思わないでください。
瞬間瞬間に生じているその思考さえも、価値判断なく見ていくこと。
思考さえも、感じてみてください
姿勢・環境
マインドフルネスが
いつ、どのような場面であっても本質的には実行可能であるとはいえ、
マインドフルネスの実行のための最低限の姿勢や環境を整えておく方が、より効果的に実行出来ると思います。
本質的には、マインドフルネスは、たとえどんなにうるさい環境であっても、痛みや苦しみのさなかにあったとしても、それそのものを価値判断なくただ見ることですから、わざわざ環境を整えたりするのは邪道であると思われるかもしれません。
しかし、私たち多くの人にとって、静かではない環境や、乱れた姿勢で一つの事に注意を向けることは困難が生じます。
他に多くの人がいる騒がしい部屋で実行することは、注意と気づきを知らないマインドフルネス初学者にとっては難しいことであり、一度難しいと思ってしまったら
「マインドフルネスは自分には無理かもしれない」と思ってしまう悪いきっかけを作り出してしまうかもしれません。
できれば、静かで、整理整頓のされた部屋で、たっぷりと時間をとって、急がず焦らず、
寝転ぶのではなく背筋を伸ばしてまっすぐに座って実行することをおすすめします。
このようなマインドフルネスのための時間を持つ事が自分の心のデトックスになり得ると感じられれば、マインドフルネスの習慣化の大きな一歩となることでしょう。
呼吸法のエクササイズ

以下に、呼吸法のエクササイズの方法を抜粋し、紹介します。
呼吸法のエクササイズ1
1.あおむけに寝るか、あるいは椅子に座るか、どちらか楽な姿勢を選んでください。座る場合は、背筋をまっすぐに伸ばし、肩を落として、肩の力を抜いてください
2.目を閉じた方が気持ちがいいと思う人は、目を閉じてください
3.息を吸い込んだときは静かにふくらみ、息を吐いたときは引っこむのを感じながら、腹部に注意を集中してください
4.まるで自分の呼吸の波乗りをしているように、息を吸い込んでいるあいだも、息を吐き出しているあいだも、呼吸のすべての瞬間に注意を集中してください
5.自分の心が呼吸から離れたことに気がついたら、そのたびに呼吸から注意をそらせたものは何かを確認してから、静かに腹部に注意を戻し、息が出たり入ったりするのを感じとってください
6.心が呼吸から離れてほかのことを考え始めるたびに、呼吸に注意を引き戻すのがあなたの仕事です。どんなことに気をとられようとも、そのたびに注意を呼吸に引き戻してください
7.このエクササイズを毎日都合のいい時間に十五分間行ってください。気乗りがしなくても、とにかく一週間続け、生活の中に瞑想法を組み入れることによって、どんなふうに感じるかを観察してください。また、毎日一定の時間を何もせずに自分の呼吸にだけ集中してすごすということについて、どんなふうに感じているかを意識してください
引用文献:J.カバットジン(著)、春木豊(訳) 『マインドフルネスストレス低減法』 2007年、北大路書房
呼吸法のエクササイズ2
1.一日のうち何回か、呼吸に注意を集中します。一度ずつ、あるいは二度ずつ息を吸ったり吐いたりするたびに、腹部を空気が通過し、ふくらんだりひっこんだりするのを感じてください。
2.注意を集中している瞬間瞬間に、わいてくる思いや感じに気をつけてください。そういう思いや感じ、あるいはそういう思いや感じを受け止めている自分に対して評価はくださずに、ただ観察してください。
3.また、ものごとに対する見方や自分に対する感じ方になんらかの変化が生じた場合も、見落とさないでください
引用文献:J.カバットジン(著)、春木豊(訳) 『マインドフルネスストレス低減法』 2007年、北大路書房
マインドフルネスのポイント
『マインドフルネスを生活の中に取り入れるための6箇条』を考えてみました。
- 上手くやろうとしないこと
- とりあえずやってみること(考えるより産むが易し)
- 気軽にやってみること
- 成果を期待しないこと
- 方法にこだわり過ぎないこと
- とりあえず続けてみること
・・・この6箇条を書いてみて思った事・・・なんとなく、睡眠に似ているような気がしました。
○眠りの状態を引き起こさない睡眠
○意識がはっきりした状態での睡眠
と言い換えても面白いかもしれません。
とにかく、それくらい気軽に気楽にやってみることがポイントです。
まとめ―こんな人におすすめ
仕事や人付き合い、日常生活でのあまりにも多くの「~すべき」に囲まれている現代人のほとんどすべての人におすすめしたいと思います。
マインドフルネスは、凝り固まった一つの考えから解放されるための良い手段にもなり得ます。
マインドフルネスを意識的に実践するのは、一日たった5分でも、3分でも良いと思います。
あるいは、「ながら瞑想」と言って、何かをするついでにマインドフルネスをすることも有効であると考えます。
例えば、毎日の通勤に使う電車の中で、座っていながらでも、つり革につかまりながらでも、マインドフルネスは実行することが出来ます。
つり革の持ち手の感覚、熱、手にかかる負担、手汗のじめっとした感じ、、、
あるいは、歩いていても出来ます。右足を出す。着地の時点での右足にかかる自重、痛み、かかとからつま先への荷重移動。。。
大げさに言ってしまえば、人生のすべてがマインドフルネスであり、瞑想です。そうでない瞬間はありません。
私たちはいつも考え、何かしています。
でも、本当にしているのは誰でしょうか?私でしょうか?
マインドフルネスは、私たちには本来何もすべきことはないことを教えてくれます。
心臓は動くべきと思って動いているのではありません。
呼吸も、するべきと思ってしているわけではありません。
それらと同じように、日々の行為の一つ一つも、自然に行われるように、
苦しい義務感や切迫感から少しでも解き放たれるように、
一人でも多くの人がマインドフルネスの奥深さに気づいてもらえたら幸いです。
カウンセリングを受けてみたい方へ
・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)



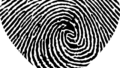
コメント