開業カウンセラーへの相談は最後の選択肢?
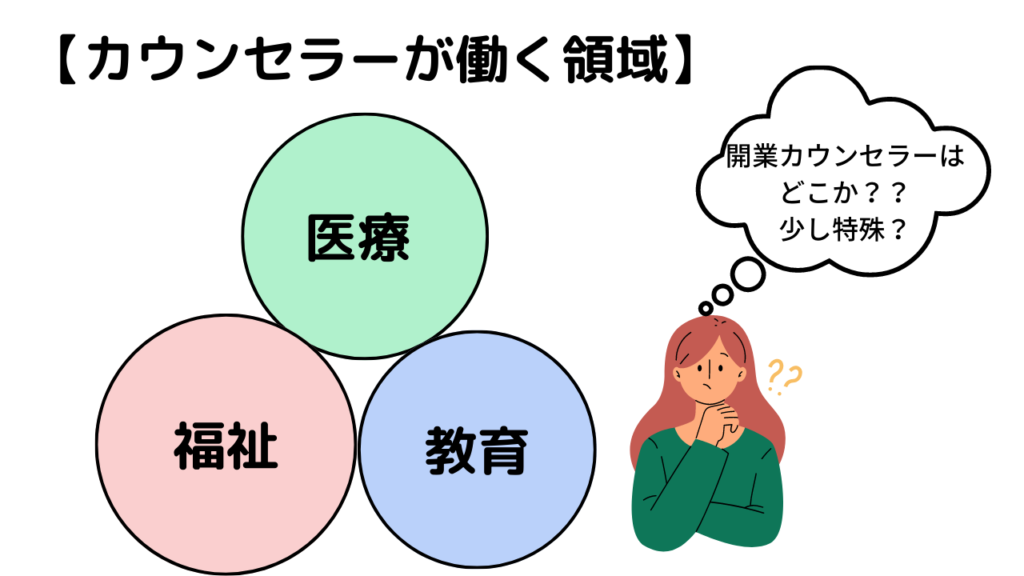
一般的に、現代の日本において、
人が悩み、心の健康を損ねる事態に陥った時に取る行動としては
- 自分一人で抱え込む。自分一人で解決しようとする
- 家族や友人などに相談する
- 各領域の専門家に相談する
- 心療内科や精神科へ行く
- 心理カウンセラーに相談する
などが挙げられます。
「自分一人で抱え込む」「自分一人で解決しようとする」人は少なくないのではないでしょうか?
潜在的には、まだまだたくさんの「本当は誰かに相談したい。助けが欲しい」と思っているけれども、具体的な相談には至っていないという人が多いと思われ、
こういった人達にもよりカウンセリングを受けやすくすることが我々資格を持ったカウンセラーの役割であると考えています。
医者への相談に限らず、心理カウンセラーに相談する時の最初の一歩も多大な勇気が必要です。
そんな背景がある中で、開業カウンセラーに最初に相談をしにいった人は少ないと思われます。まずは身近な医療機関、学校組織、福祉施設、家族や友人に相談してみる人が多いと思われます。
そういった意味で、現状、開業カウンセラーの位置づけは最後のセーフティネットと考えます。
(*開業カウンセラーが第一候補に挙がるようにするのが私の個人的な目標ではありますが)
「今まであらゆるところに相談した。服薬した。でも効果を感じなかった。
カウンセリングも受けた。これも効果を感じなかった。。。」
そういう時に、開業カウンセラーのプロフィールやブログやコラムでの発言・考え方に共感を得て、「この人ならもしかして」と思ってアクセスしていただける方が多いように感じています。
そういった意味を含めて、「最後のセーフティネット」と表現してみました。
このコラムでは、開業カウンセラーとは何なのか?
開業カウンセラーの特殊性と強みについて述べていきたいと思います。
開業カウンセラーとは何か?
臨床心理士や公認心理師の資格を持って、個人でカウンセリングルームを開業し、カウンセリング業務を行う者のことを指します。
実際には、臨床心理士や公認心理師の資格をもっていなくてもカウンセリング業務を行うことは出来ます(これらの資格が業務独占資格ではないため)。
ですが、あえてこのコラムにおいては、臨床心理士や公認心理師の資格を持っていることが開業カウンセラーであることの条件として必須のものとして強調したいと思います。
心理カウンセリング業務は、相応の知識と経験が必要なものであって、現状日本においては、これらの資格が最も「知識と経験」があることを保証するものであるからです。
臨床心理士や公認心理師の資格は、簡単に取得することができるものではありません。一般的には、少なくとも大学の4年間と大学院の2年間で心理学(主に臨床心理学)の勉強と、臨床経験を経て、心理カウンセラー足り得るかをテストされなければなりません。
私の場合は、大学院の時点で、「自分はカウンセラーに向いていない」と思い、一度は諦めました。向いていないと思いながらは出来ない仕事なので、今現在は「向いていないことはない」と思いながら公認心理師として心理カウンセリングを行っております。
カウンセラーのいる場所と役割
心理カウンセラーが働く場所と、働く場所に応じた役割について、以下の表にまとめます。
| 働く場所 | 役割 | |
| 開業カウンセラー | カウンセラーの自宅や、ビルやマンションなどの一室 | ・服薬に抵抗のある人、服薬に効果を感じられない人、何らかの理由で医療機関やその他施設のカウンセリングを受けていない人への心理カウンセリングの提供 |
| スクールカウンセラー | 学校 | ・学校で児童生徒、保護者や先生などに対してカウンセリングを行う ・単にカウンセリングを行うだけでなく、心理職以外の職種(学校の先生、医療機関など)や保護者との連携を行う ・場合によっては学校の環境を観察し、環境調整のための助言などを求められることもある |
| 企業内カウンセラー | 企業 | ・企業で働く社員等に対してカウンセリング、メンタルヘルスチェックを行う |
| 病院・メンタルクリニックに勤務するカウンセラー | 病院、メンタルクリニック | ・医師との連携、情報交換 ・服薬との奏功を目的として、あるいは、服薬に効果が認められない患者さんへのカウンセリング。心因が要因となっていると思われる場合に対応する。 |
| 福祉施設に勤務するカウンセラー | 児童福祉施設、老人福祉施設等 | ・学校でも病院でも企業でもなく、福祉施設での利用者様の観察、見守りを中心とした支援を行う。 ・主に利用者様の心のケアを目的として、施設への通所などと並行してカウンセリングサービスを提供することがある。 |
このように、カウンセラーは医療・福祉・教育の各領域で広範囲に活躍しております。
開業カウンセラーは「働く場所」において特殊であると言えます。
開業カウンセラーの場合は、クライアントとの距離が、良くも悪くも近くなりやすいです。
カウンセラーとクライアントの間にはある程度の「守り」が必要です。その守りとは、制度や規則、カウンセラーまでの距離感などが挙げられますが、開業カウンセラーではこの守りが薄く、利用するに当たってためらいが生じやすいとも言えます。
その反面、この守りを上手く担保する事さえ出来れば、開業カウンセラーは身近な相談者として機能していくのではないかと考えています。
開業カウンセラーの専門性・強み
上記の表からも察することが出来ますが、
開業カウンセラーは、カウンセリングを受けたい人にとって、第一選択肢になることは少ないと考えられます。
まずは、最も身近な医療・福祉・教育領域のそれぞれの専門家に相談しに行くからです。
では、開業カウンセラーの専門性はどんなところにあるのでしょうか?
私なりに考えてみました↓
- 独自性が強い
- 組織的なしがらみからある程度自由
「独自性の強さ」・「ある程度の自由度」
他の施設、機関で働いているカウンセラーと違って、よりカウンセラー独自の
- 見た目や経歴
- 価値観・考え方
- 人間性
- 治療方針
などのプロフィールがオープンにされやすいと思います。
これが、組織に属しているカウンセラーだと中々こうはいきません。
もちろん、これに関しては賛否両論、善し悪しが分かれるところではありますが、
開業カウンセラーの元へ訪れる人の中には、「カウンセラーのプロフィールを見て惹かれるものがあった」、「コラムやブログ、SNSでの発言に共感を得た」といった理由で来られる方が少なくありません。
「カウンセラーであれば誰でも良い」と思わないクライアントにとっては、カウンセラーを選ぶ際の材料が豊富であり、後悔しないカウンセラー選びにつながりやすいと思われます。
カウンセラーの経歴や価値観、人間性はどのようにカウンセリングに影響するか?
カウンセラーの仕事の基本は、
クライアントの話をきくこと
であって、カウンセラーがどういう人物であるかは関係ないと考える人もいるかもしれません。
・・・が、私は必ずしもそうではないと思っています。
例えば、
カウンセラー自身がある程度の苦難を乗り越え、様々な世界を見てきたからこそ、本当の意味での深い共感が出来るということも、実際にあります。
共感の「深い」、「浅い」は目に見えるものではありませんが、クライアントは確実に感じるものです。
カウンセラーの発言や、経歴などを見て、「共感してもらえそうか?」を判断するのも、カウンセラー選びの一つのポイントになるでしょう。
開業カウンセラーの課題
料金設定の高さや、敷居の高さが、開業カウンセラーがこれから解決していかなければならない課題です。
そのために出来る努力として、
当カウンセリングオフィスでは、
「料金設定をなるべく安くすること」と、「日々の臨床実践から得られた知見をホームページを通して世に広めること」を重視して一人でも多くの人のお役に立てるように尽力しています。
タイトルにもあるように、
「服薬しても良くならなかった」人はもちろんのこと、
「今まで色んな手段を通してきたけど上手くいかなかった、改善しなかった」という人は、是非一度ご相談下さい。
カウンセリングを受けてみたい方へ
・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)
*TwitterのDMや公式ラインからのお問い合わせも受け付けております!!

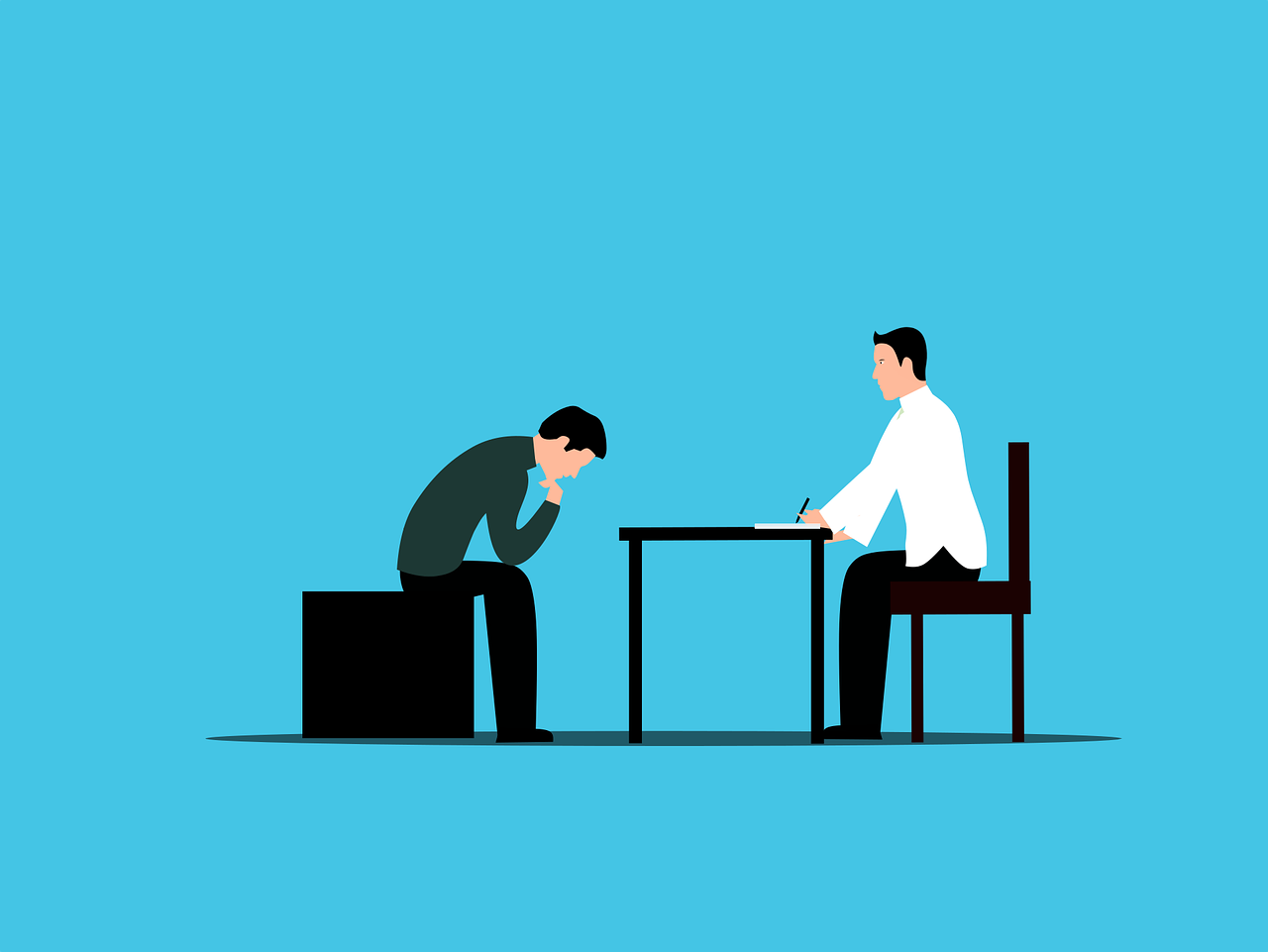


コメント