本コラムにおいては、カウンセリングの基本である「共感」について思うことをまとめていきます。
他者との共感的な関わりの不足が、現代社会の病理の一つであると昨今感じられるからです。
同情して欲しくない
いくらかのクライアントさんからは

友達とかに相談しても、「大丈夫だよ」とか「全然そんなことないよ」「気にしないでいいよ」とか言われるけど、どうせそんなこと思ってないくせに、って思っちゃう。
どうせみんな同情してるだけなんでしょ。同情ですらない、表面的な言葉なんて言われても信じられない。どうせ思ってないくせに。私が人を信じられないのがいけないんですかね?
のようなことをおっしゃられることがあります。
よくある日常的なコミュニケーション、なんとなしに使う言葉ですが、「大丈夫だよ」「そんなことないよ」という言葉に違和感を覚えることもあります。

だから私は人に相談したりとか、悩みを言わないようになりました。言っても無駄だから。どうせ分かってくれないし、表面的なことしか言われないだろうから。
すべてのクライアントさんがこのように感じるわけではありません。
しかし、このように語るクライアントさんの多くは、カウンセリングでもしばしば細かい説明を省略して話す傾向があるように思われます。どこか投げやりです。
私は、どのようなクライアントさんからでも、(特にカウンセリングの初期は)できるだけ具体的な情報を聞き取ります。結構、かなり積極的に情報を収集します。それも、かなりの興味と関心をもって。
例えば、
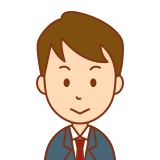
仕事で困ってます
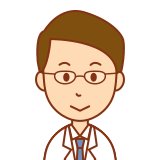
何のお仕事ですか?
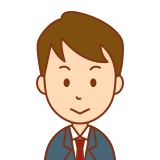
え、普通に…。ピッキングのバイトです
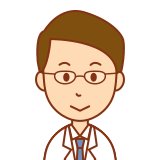
ピッキングの仕事されてるんですね。それで、ピッキングの仕事中のどんなことに困っているんでしょう?
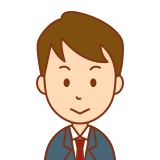
え、なんだろう。僕のことをよく怒ってくる人がいるんですよね。僕の仕事が遅いのか分からないんですけど。
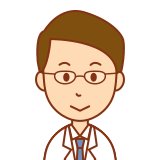
どんな風に怒ってくるんでしょう?直接的な注意をされるのか、それとも、舌打ちをされたり無視されたりちょっと陰湿な感じなのでしょうか?
…と、このような感じでかなり細かい情報収集をカウンセリングではまずします。職場での人間関係をまずはここで聞いていますが、この後さらに、このクライアントさんが普段具体的にどのような仕事をしているのかを聞いていきたいところです。職場の同僚に怒られる(?)に足る理由があるのかどうか、そういった事実確認が必要です。
あまりにしつこく聞きすぎるとそれはそれで聞かれる方もしんどいので、もちろんそのあたりのことも意識しながら臨機応変に聞いていきます。
このように細かく聞く理由は、カウンセリングを単なる「同情の時間」にしたくないからです。
共感は同情とは全く異なる
同情について、
<前提知識の共有や情報収集、状況把握を怠った状態で、相手の気持ちに表面的に寄り添おうとすること>
と私は定義します。
一方で共感とは、
<細かく相手の状況をできる限り把握した上で、相手の気持ちに想像力を働かせて寄り添おうとすること>
であると私は思います。
当然、カウンセリングの中では同情ではなく共感ができるように意識を働かせます。
また、共感とは意識的なものであるのみならず、自然発生的なものでもあります。
事実である情報を聞いていけば自ずから共感は芽生えます。
事実である情報さえないのに、共感は芽生えません。もし何の情報も聞かずに共感できる人がいるとすれば、それは超能力者とか霊能力者とかの類です。
同情しちゃダメなのか?
共感についてこのように述べると、まるで同情することが悪いことのようにも見えてしまいますが、必ずしも同情することがダメなことであるとも思いません。
そもそもこの世の中には「〇〇してはいけない」なんて決まりはありません。あるとしたら、それは人間が人間の都合で勝手に作り上げてきたものです。
心理的治療においては、何が功を奏するのかは最後まで分からないところがあります。
一見「良くなった」ように見えて、実はとんでもないどんでん返しがあったり、
あるいはその逆に、
一見「悪くなった」ように見えて、長期的には良いことであったり…。
まさに、禍福は糾える縄の如しです。
「同情なんてしてほしくない」と言う人がいる一方で、
「同情してほしい」と思っている人もいるかもしれないのです。
できる限り何も決めつけずに、原理原則とか世の中の当たり前に縛られないようにしたいと個人的には思います。
人の気持ちに寄り添う余裕がなくなりつつある時代
「共感」はカウンセリングの基本ですが、心理カウンセリングが現代の仕事として成立しているのは、共感的に話を聞くことができる環境が減ってきているからではないでしょうか?
共感には、上述の定義からすると、どうしても相手の話を丁寧に聞く時間的余裕と空間的余裕、そして心理的余裕が必要です。
カウンセリングのメリットとは、これら3つの余裕が保証されているという点です。
・決められた時間話をすることができる(時間的余裕)
・他者からの邪魔の入らない、秘密保持が保証された空間で話をすることができる(空間的余裕)
・人の話を共感的に聞く技術、知識や経験、相手への関心、困っている人の役に立ちたいと積極的に思う心を持っているプロであるということ(心理的余裕)
カウンセラーという仕事としてであれば、これら3つを満たすことは可能です。(もちろん、カウンセラーであっても日々の研鑽と反省が欠かせません。これらを欠かすと話を聞く余裕のないカウンセラーになってしまいます)
しかし、そもそもカウンセラーという仕事が存在しなくとも、これらの余裕が常に家庭や社会の中にあれば理想的ですよね。
残念ながら、現代社会においてはこの理想が叶えられない現実的な事情が多くあるようです。特に、複雑な家庭環境で幼少期を過ごしてきたクライアントさんの話を聞く時にそう感じることがあります。
しかし、このテーマは大きすぎて本コラムの中では扱いきれないでしょう。
現実的に、カウンセラーである私にできることは、上記3つの余裕を用意して、必要とする人にカウンセリングサービスを提供することくらいです。
カウンセリングの案内
*カウンセリングオフィスともしびは事前予約制です。
・ご予約はこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)から。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)




コメント