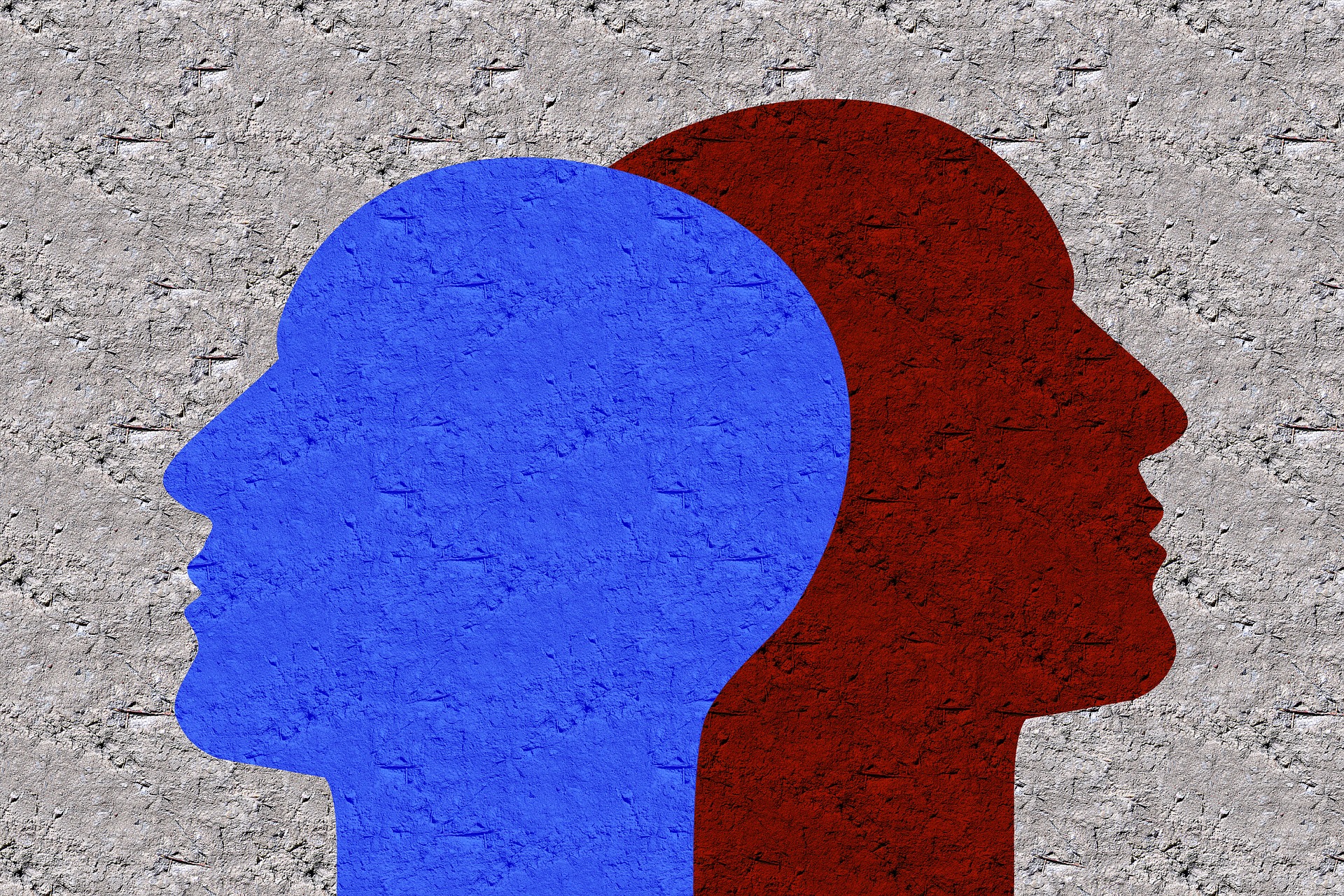双極性障害とは
「躁状態」と「うつ状態」を繰り返し、各状態におけるその行動の質と量の過剰や不足によって、生活に支障をきたす障害です。
双極性障害と診断されるためには、躁症状が認められることが前提です。
躁症状にも軽躁と躁という2つの区別があります。軽躁は躁と違い、社会的な問題に発展しにくく、患者本人や周囲の人も気づきにくいですが、軽躁の方が生きやすいというわけではありません。軽躁が自覚されにくいために、症状をコントロールすることに対して抵抗や困難を感じる人が多いためです。
初期に現れる症状がうつの時に、うつ病として診断され、抗うつ薬を服薬することによって薬物躁転してしまい、その時に初めて双極性障害と気づく人もいます。
また、躁症状が「単に元気の良い状態」であると勘違いしてしまうことで、双極性障害の発覚が遠くなることもしばしばあります。
診断が難しい障害ですので、少しでも違和感を持ったら一度相談してみて下さい。
【注意】うつ病とは違います
上述のように、双極性障害と診断されるためには、躁症状が認められる必要があります。
躁の状態とうつの状態を繰返しますが、人によってその状態が維持される期間も程度も異なります。
うつの状態だけを切り取ってみることが出来ず、その背後に、躁状態の時の過ごし方などによる影響も潜んでいます。
また、うつ病とは治療法も薬も異なります。
そのため、正確な鑑別をしなければなりません。実態は双極性障害であるのに、抗うつ薬を服薬し続けることは危険なことです。
まだまだ双極性障害に関する研究は少なく、分かっていないことが多い障害ですが、罹患率はうつ病の方がやや多いことが分かっています↓
| うつ病 | 双極性障害 | |
| 罹患率 | 約8% | 約1% |
| 再発率 | 1回目:50% 2回目:70% 3回目:90% | 1年間:48~60% 5年間:81~91% |
ちなみに、うつ病の再発率はとても高く、1度うつ病になると約半数の人が再び罹患してしまいます。うつ病も放置せず、再発予防をしっかり考える必要がある病気です。
双極性障害と似ている病気
うつ病以外に双極性障害と間違われやすい病気があります。
「境界性パーソナリティ障害」や「統合失調症」です。
境界性パーソナリティ障害についての説明はこちらを参照してください。
注意サイン
躁症状とうつ症状の2つの注意サイン・症状を以下に記します。
躁症状の注意サイン
- 高揚・もしくは怒りっぽい気分、加えて活力が増加した状態
- 自尊心の肥大、または誇大
- 睡眠欲求の減少
- 普段より多弁であるか、喋り続けようとする切迫感
- いくつものアイディアが次々と浮かんでくる体験
- 注意散漫
- 目的を伴う活動の増加、または焦っている様子
- 困った結果に繋がる可能性が高い活動に熱中する
うつ症状の注意サイン
- 抑うつ気分
- 興味または喜びの著しい減退
- 食欲の減退または増加
- 不眠または過眠
- 他者から観察される落ち着かなさ・動きの乏しさ
- 疲労感または気力の減退
- 無価値感あるいは罪責感
- 思考力・集中力の減退、決断困難
- 希死念慮
躁状態には、「軽躁状態」と呼ばれる状態もある
ハイテンションであるが、本人も周囲の人も躁状態ほど困らないのが「軽躁状態」です。
躁状態ほど困らないのであれば、問題ないようにも思えますが、そうではありません。
躁の程度が軽い代わりに、うつ状態が長いのが特徴です。
また、躁の程度が軽いという特徴があるために、
「双極性障害であるという自覚を持ちにくい」
「双極性障害の発見が遅れる」
といった事になりがちです。
原因
原因は明確には解明されていませんが、遺伝的要因が基盤にあることが分かっています。
そこにさらに環境要因(ストレス、身近な人の死、仕事や人間関係における失敗や傷つき、昇進・転職・結婚などの一般的に良いとされる出来事)が加わることで発症しやすくなるとされています。
効果的な治療法

薬物療法を基盤として、
「双極性障害の心理教育」「対人関係・社会リズム療法」「認知療法」「家族療法」などの心理療法が有効であるとされています。
薬物療法は必ず主治医と相談の上で適切に行っていく必要があるものです。
双極性障害の薬は「気分安定薬(リチウム、バルプロ酸ナトリウム、ラミクタールなど)」「抗精神病薬」「抗不安薬」「睡眠薬」などの薬を組み合わせて処方されます。それぞれの薬には処方される意味がありますので、主治医にその理由を聞いておくことも重要です。
ここでは簡単に述べるにとどめますが、、、
気分安定薬は躁状態に対してもうつ状態に対しても用いられ、予防効果もあります。
抗精神病薬は急な躁転が見られた際に用いられます。
当事業所では、薬物療法を補う形での心理療法を提供することができます。以上に挙げた4つの心理療法を適切に組み合わせて提供しておりますので、ご相談下さい。
↓こちらの動画でも、双極性障害に心理療法が有効かどうかを考察していますので、参考にして下さい。
↓こちらの動画では、双極性障害の治療目標について話しています
双極性障害の心理教育とは何か?
「教育」という言葉が入っていることから、カウンセラーから相談者様に一方的に教えたりアドバイスしたりする、、、といったニュアンスが強く感じられるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
むしろ、カウンセラーが相談者様から教えられることが多いです。
相談者様の「生育歴(どのような家庭に生まれ、どのように育ってきたのか)」「性格(双極性障害を発症しやすい性格なのかどうか)」「双極性障害を発症するきっかけとなった出来事」・・・など、
個々の相談者様の状況をカウンセラー側も正確に把握した上で、双極性障害に関する正しい知識を与え、偏見などを取り去っていくことから始めます。
相談者様の双極性障害に関する知識や理解が深まって行くにつれて、障害に対する治療の抵抗性も和らぎ、前向きに治療に取り組むことが出来るようになっていきます。
この「前向きに治療に取り組む姿勢」が、双極性障害の治療に限らず、状態の回復にとって非常に重要な役割を持っています。
心理教育は、この「前向きに治療に取り組む姿勢」を相談者様だけでなく、周囲の家族や友人など、出来るだけ多くの相談者様を取り巻く人々に持って頂くためにも必要なものです。
当事業所では、双極性障害でお悩みの方には、この「心理教育」の部分を治療の序盤における主要な戦略として提供していきます。
カウンセリングを受けてみたい方へ
・ご予約はこちらから、または直接お電話(090-6079-0783)からお願いします。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから、または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)
・もちろん、直接店舗へ来て頂いてもOKです!!