「不安」は私にとって最もよく聞く言葉の一つです。本コラムではこの不安について取り上げ、不安がありながらも人としてどう生きていくべきか考えていきたいと思います。
不安とは何か?
危険の予測によって引き起こされる心配の感情。危険は内的なことも外的なこともある。
ベンジャミン・J・サドック(著)、ヴァージニア・A・サドック(著)、融道男(監訳)、岩脇淳(監訳) 『カプラン臨床精神医学ハンドブック DSM-4-TR診断基準による診療の手引き』28頁 メディカルサイエンスインターナショナル、2017年
不安と言う状態をかなり適切に表現している文章だと思います。
不安はよく恐怖という言葉とセットで用いられます。
「恐怖が具体的な対象を持つのに対して(例:高所恐怖、対人恐怖、蛇恐怖…等)、
不安は具体的な対象がなく漠然としたものである」
とよく言われています。
しかし私は、不安にも恐怖の対象があると思います。恐怖ほど明確ではないものの、対象がなければ不安も抱くことはできないでしょう。
もっと言うと、
不安と言う状態は、対象はあるものの、その対象をうまく言語化できない状態でもあると思います。
あるいは、言語化したくない、認めたくないという心理も働いているのでしょう。
最も多く出会う主訴
精神的な訴えに着目すると、私が今まで最も多く出会った主訴は圧倒的に「不安」であると思います。
なぜこんなにも不安を感じる人が多いのか?
想像に難くはありません。今の世を生きていれば、不安を感じないほうがおかしいというものです。
また、社会経済的な要因だけでなく、性格的な要因も考えられます。私自身も子どもの頃は特に心配性であり、かつあがり症でした。
不安の強度、感じ方や種類は実は人によって様々です。
また、不安にはいくつかの種類があるようにも思われます。あえて不安をいくつかの種類に分類してみます↓
例えば、
A.現実的な不安(了解可能な不安)
→一般に多くの人が理解を示すことの出来る不安
例1)全く勉強をしていないので、明日のテストが不安
例2)地震のニュースを見て、大地震が起きるかもしれない不安
例3)寝不足なので、交通事故に会うかもしれない
B.非現実的な不安
→単に妄想じみた不安というだけではない。現実的な不安に内容は似ていても、その成立過程に不思議なところがある
例1)毎日お祈りをしていなければ大地震が起きてしまうかもしれない
例2)いつもと違うルーティンをしたので、交通事故に会うかもしれない
C.漠然とした不安
→「なんとなく、漠然とした不安」としか言いようのない不安。
です。
これら3種の不安の出現頻度として、
「非現実的な不安」が見られるのは珍しいと思います。しかし、それでも上述の例に近いことを訴える方は一定数おられます。
「現実的な不安」と「漠然とした不安」は、どちらも同じくらい見られるような気がします。自分自身のことを考えてみても、ある時ふと漠然とした不安を抱えている自分を発見したりします。物事の整理が進んでいくうちに現実的な不安が背景に潜んでいると気づくこともあります。
*むろん、これら不安の出現頻度などは統計的に数えているものではなく、あくまで私の感覚的な話ですのでご理解ください。
さて、後述するAさんは「非現実的な不安」のことを「偽の不安」とも表現していました。
この「偽の不安」という表現が、それを聞いた当初の私にとって非常に興味深かったため、以下にまとめたいと思います。
偽の不安 VS 本物の不安
私が関わったことがある強迫性障害のクライアントAさんが、治療経過中に以下のように不安についての気づきを表現していました。
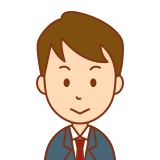
最近、「偽の不安」だと途中で分かって脅迫行為をやめるに至ったことがありました。
このクライアントAさんは「偽の不安」とさらっと表現していましたが、私には結構インパクトのある表現でした。今まで私はAさんとの会話の中で「偽の不安」という言葉を使ったことがなかったからです。
つまり、この表現はAさん自らが発見した事実なのでしょう。
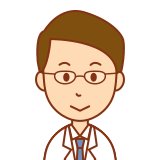
「偽の不安」とはちょっと面白い表現だと思いました。つまり、不安には偽の不安と、それに対する本物の不安、現実的な不安とが在るということでしょうか。Aさんが自らそのような表現を使われたことが新鮮でした。
クライアントAさんはつまり、不安には
①非現実的で起こり得る可能性の低い、ごくごく個人的なレベルの不安
②現実的で起こり得る可能性の高い、他者にも了解可能なレベルの不安
この2つがあるのではないかということでした。
私は<なるほど>と感心させられました。
さらにAさんが続けて曰く
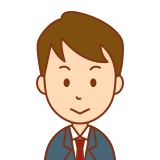
「偽の不安」に振り回されていたけれど、もっとより「現実的な差し迫った不安」が同時にありまして、そちらの不安に対処するために偽の不安については諦めました。
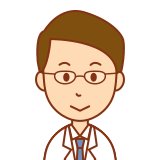
つまり、いつもなら「偽の不安」への途方もない対処に追われていたけれども、偽の不安をあきらめざるを得ない「現実的な不安」が、偽の不安よりも勝っていたということですね。
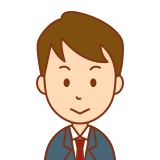
そんな感じです。
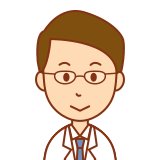
現実的な不安は我々にとって役に立つこともあるのですね
「不安」と「愛着」の関連性
不安は人間に備わっている大事な機能の一つであるとも思います。
上述したように、現実的な不安は我々にとって役に立つこともあるようです。
本来それは生きる上で邪魔になるものではないのでしょうが、それが邪魔になっていたり問題になっている人がいることもまた事実です。
人は本来、不安があっても生きていく力を環境から身に着けていきます。それも、人生におけるだいぶ初期の段階において。
幼少期における親との愛着形成の段階は、不安において最も重要な要素である、ということも覚書として付け加えておきたいところです。
参考コラム:愛着障害と発達障害、境界性パーソナリティー障害
参考・引用文献
カウンセリングの案内
*カウンセリングオフィスともしびは事前予約制です。営業日は土曜、日曜、月曜日です(時間応相談)。
・ご予約はこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)から。
・「どんなことをするのか分からない」「直接具体的な内容を聞いてみたい」「カウンセラーの声を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
→お問い合わせはこちらから。または、直接お電話(090-6079-0783)からでも対応可能です(不在の場合は24時間以内に折り返しのお電話をします)




コメント